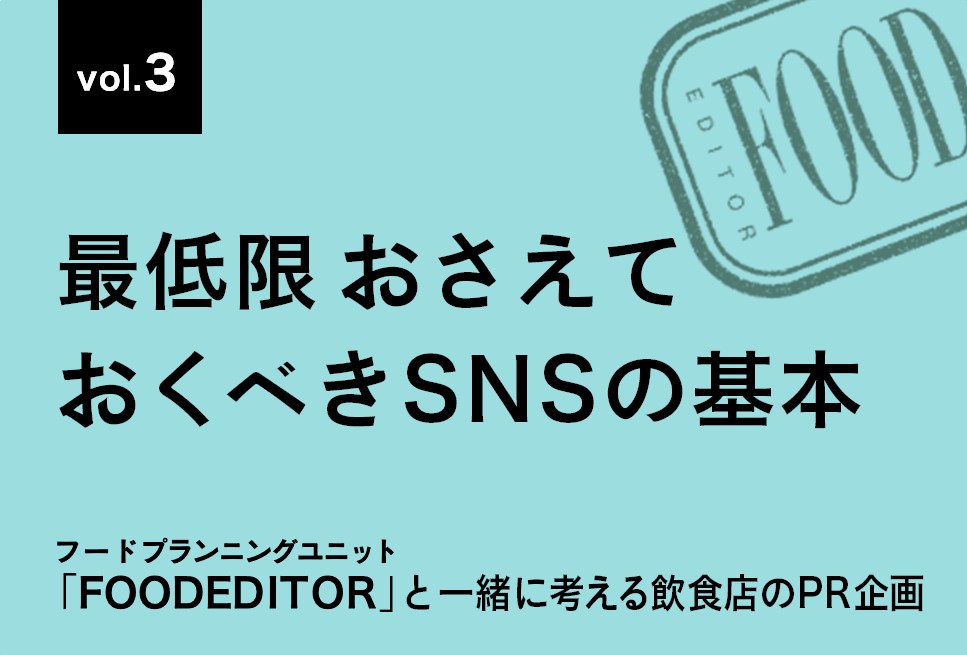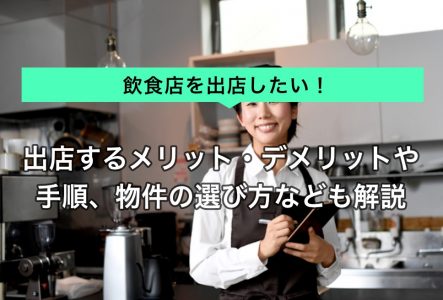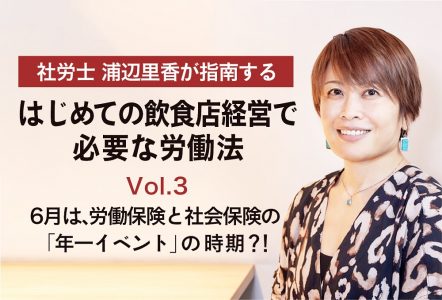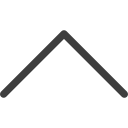敷金と保証金の違いは?店舗の賃貸借契約で預託する金銭にまつわる話
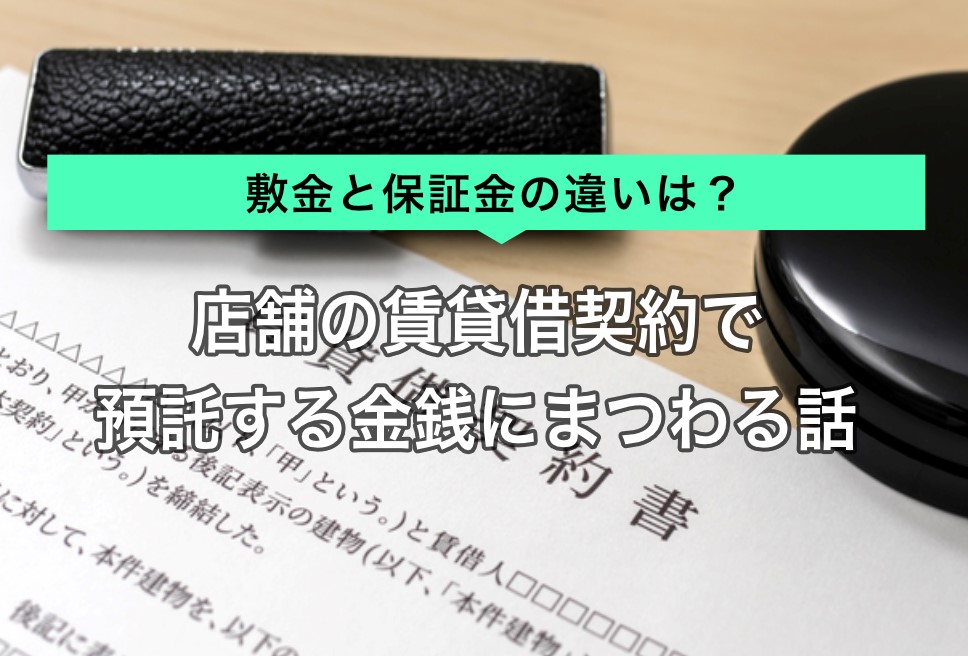
店舗物件の賃貸借契約を締結する際に支払う金銭には造作譲渡代金(居抜き物件の場合)、前賃料・管理共益費、礼金、敷金・保証金、仲介手数料、保証会社初回保証料、火災保険料などがあります。この中でも特に敷金や保証金は、高額になる傾向があるものの、その詳細なことについては、あまりよく理解していない人が多いという印象です。本記事では、事前に理解をしてから店舗物件の賃貸借契約を締結することを目的として、敷金や保証金についてのあれこれを網羅的にわかりやすく解説していきます。
目次
◆敷金とは何か?
敷金については、民法に記載がありますので、まずはそこを確認してみたいと思います。民法第622条の2に「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、 賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」との規定がされています。端的に物件を貸す側のリスクヘッジのためのお金であることが分かります。特に店舗物件の場合については、経営の状態が良くないと賃料、管理共益費などが未払いとなってしまい賃貸人に大きなリスクが伴ってしまいます。また、物件を退去する際には、賃借人は原状回復(多くの場合は、物件を建設当初のスケルトン状態に戻すための工事を行う)する義務を負うのですが、賃借人にこの費用の支払い能力がなければ、預かっている敷金を原状回復費用に充てることになります。この敷金は、礼金のように賃貸人の収入とはならない(あくまで預り金となる)ので、課税(消費税)の対象とはなりません。不課税取引(注1)となります。
(注1)不課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に当たらない取引は、不課税取引といいます。一方で、非課税取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引がそれに該当します。
参考:非課税と不課税の違い|国税庁
◆敷金と保証金の違い
敷金と保証金の違いは何でしょうか。民法第622条の2の括弧書きに「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、 賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されているので、賃貸人に対して預託する金銭が同趣旨であれば、保証金と敷金は、法的に同じ性質のものであると言うことができます。首都圏において、店舗などの事業用物件については、住宅(住宅は敷金であることがほとんどです)とは異なり保証金の名称が多いのが特徴です。
◆保証金の名称の由来
今日では敷金と保証金は、同じ性質のものとして扱われることが多いですが、保証金の名称の由来については建設協力金からきているようです。遡ること明治時代後期から1960年代、大手不動産会社が貸しビルを建設するため、賃借人から敷金のほかに建設協力金(建設費用)を預かり、一定期間は無利子で、その後は利子をつけて返済するとされたもので、これにより賃借人は入居する(賃借する)権利を得ることができました。1970年代に入ると、日本経済の復興や高度経済成長によって建設協力金に頼ることなく独自に(自前で)建設費用を調達して貸ビルを建設することができるようになると賃借できることを保証することが減っていきました。保証金は、その時の商慣行の名残と言えます。この保証金ですが、内容の如何によっては、賃貸借契約とは別に締結された金銭消費貸借契約とみなされることがあります。
◆償却と敷引き(しきびき)
保証金の場合、賃貸借契約書に償却の記載があることがほとんどです。退去時、債務の清算に加えて償却費が差し引かれ、保証金に残金があれば賃借人に返還されることとなります。償却費は戻ってこないものになります。償却のパターンとしては、年〇%を償却、退去時に賃料の〇ヵ月分、保証金の〇%相当額を償却、など店舗物件によって異なります。年償却(1年ごとに償却するの意)の場合は、契約更新時に追加にて償却分を補填しなければならないケースが多いです。一方で、敷引き(しきびき)は、関西地方をはじめとした西日本の賃貸借契約において使用されることが多いものです。東日本においては使用されることはあまりないため、馴染みが薄いのが現状です。敷引きは、債務がない場合であっても返還されることはないという意味で償却と同様と考えてよいかと思います。
◆敷金・保証金の相場はどのくらい?
一般的に住宅物件の場合は、賃料の1~2ヶ月分が相場になるのですが、店舗物件の場合は、賃貸人のリスクが大きくそれを保全する必要があるため3~10ヶ月分程度となることが多いです。相場については、店舗物件によって差が大きいのが実情です。人気駅や駅近の立地が良い物件などは、高額になる傾向があり、賃料の10ヶ月分を超えるものも存在します。このような店舗物件は、物件を取得するために多額の資金が必要となってしまうため、個人の新規開業の方には、なかなか手が出しづらいかと思います。物件取得費をできる限り抑えたい方は、例えば、駅から離れているけれど人通りが多い物件、空中階だけど視認性がよい物件といったように集客がしやすいかどうかの視点で、人気駅や駅近の立地が良い物件にこだわらずに幅広く物件を探してみてはいかがでしょうか。
◆賃料が増減されると敷金・保証金はどうなるのか。
賃料が合意によって増減されたとしても、原則として、賃借人が追加で賃貸人に対し、敷金・保証金を預け入れる義務が負うことや賃貸人が賃借人に一部を返還する義務を負うことありませんが、例外として、賃貸借契約書に「賃料が増額された場合、乙は、〇〇に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額との差額を、保証金に補填するものとする。」などの規定がある場合には、賃借人が追加にて支払う義務が発生してしまいます。
◆賃貸人が変更(物件の所有権が移転)となった場合
物件の売買によって賃貸人が変更となった場合、敷金・保証金は新賃貸人に受け継がれることになります。つまり賃貸借契約と一緒に移転をすることになります。敷金・保証金が承継されるので賃借人に不利益はないです。
◆敷金・保証金と相続の関係
敷金・保証金と相続の関係について、3つのパターンについて、それぞれ説明をしていきます。
◇賃貸借契約が終了した「後」に賃貸人が亡くなった場合
賃貸借契約が終了しているため、敷金・保証金の返還債務は金銭債務となります。この返還債務は、相続人が承継することになります。原則として、債務は遺産分割の対象とならないので、この金銭債務は、共同相続人がいる場合、各共同相続人が、その相続分に応じて承継することとなります。
◇賃貸借契約が終了する「前」に賃貸人が亡くなった場合(遺産分割「前」)
共同相続人がいる場合、返還債務は、不可分債務となります。つまり、遺産分割前に賃貸借契約が終了した場合、各相続人は連帯債務者となり、賃借人に対して、返還債務の全額を負うこととなります。
◇賃貸借契約が終了する「前」に賃貸人が亡くなった場合(遺産分割「後」)
遺産分割をすることによって、相続財産の所有権が確定することになります。物件の所有権が被相続人から相続財産の所有者へ移転します。敷金・保証金の返還債務が売買などで移転するように相続においても同様に移転して相続財産の所有者のみが返還債務を負います。これによって他の相続人は、返還債務を負わないことになります。
◆解約した場合、敷金・保証金はすぐ返還される?
物件の賃貸借契約の解約した場合、敷金・保証金がすぐに返還されるとは限りません。民法第622条の2には、以下の規定がされています。
「次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
1.賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
2.賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」
敷金・保証金の返還を賃貸人に請求するためには、物件を原状回復(スケルトン工事)した上で明け渡しを完了させておかなければなりません。つまり、物件の明渡しと敷金・保証金返還請求は同時履行の関係にはなく、物件の明渡しが先で、明け渡し後に還請請求権が発生するということです。
敷金・保証金の返還時期は賃貸借契約書の契約内容によっても異なります(民法の当該規定は任意規定となるので賃貸借契約書に別に規定がある場合には、そちらが優先されることになります)ので注意が必要です。また、原状回復工事の期間が長引いてしまった場合、敷金・保証金が返還される時期も先になってしまうので、原状回復工事は、事前に計画を立てて進めておきましょう。
◆退去時に敷金・保証金が返還されないケース
退去時に賃貸人に預託している敷金・保証金は、無事に返還されるのでしょうか。そう疑問に思う人もいるかと思います。ここでは、敷金・保証金が返還されないケースについて、説明をしていきます。
◇賃借中の物件が競売で落札された場合
賃貸借契約の相手方である賃貸人が何らかの理由によって債務(借金)を返済することができなくなってしまった場合、債権者が債務(借金)を回収するために、裁判所に対し、抵当権が設定されている物件を競売にかけることを申立てるということがあります。任意売却(裁判所が介入しない般市場にて物件を売買取引する)の場合や競売にかけられたとしても賃借人が対抗要件を具備している(抵当権が設定される前に物件の引渡しが行われている)場合は問題がないのですが、抵当権が設定された後に物件の引き渡しが行われた場合、買受人(競落人)に対して、賃借権を対抗できないので、敷金・保証金の返還を請求することができません。例外として、保証金が敷金と同様の性質ではなく、消費貸借としての性質がある場合、返還義務は買受人(競落人)に承継されないので注意が必要となります。消費貸借としての性質があるかどうかについては、保証金の金額、趣旨、近隣の相場など総合的に見て判断されることになります。
◇敷金・保証金の額≦賃借人の債務の額の場合
退去時、規定の償却額を償却して、その際に滞納賃料、管理・共益費や原状回復工事に要する費用、その他未払金などがあれば、これらを差し引いた残金が返還されるのですが、預託している敷金・保証金の額≦差し引かれる金額(賃借人の債務)となった場合は、何も返還されないことになります。預託している敷金・保証金で債務がまかないきれない場合は、追加にて不足額を支払うよう請求されることになります。
◆敷金や保証金の返還される額を減らさないためにすること
店舗物件の場合は、償却もあるため、預け入れている敷金や保証金の全額が返却されるということは、ほとんどありません。しかし、できる限り、返還額を減らさないための必要な努力や注意すべきことはあります。
◇可能な限り原状回復費用を抑える。
店舗物件は、住宅物件とは異なり、不特定多数の人が物件に出入りするため、汚損や破損のリスクが高いと言えます。また、油を使用する業態の場合は、排気口周辺の壁や排水管に汚れが蓄積するため、このことも原状回復費用に影響を及ぼします。定期的な清掃を実施して退去時のクリーニング費用を抑えるような取り組みをしましょう。特に原状回復費用が高額になる要素として、躯体部分の開口があります。鉄筋コンクリート造(RC)の建物の壁面を開口してしまうと(仮に物件所有者が開口について承諾をしたとしても)鉄筋それ自体を切断することになり、原状回復費用が高額になってしまいます。そうなってしまうと、敷金や保証金の返還額が減ってしまいますので、極力、既存の開口部分を利用するといったことも重要となります。
◇居抜き物件として造作譲渡する。
居抜き物件として造作譲渡をすることができれば、原状回復義務を譲渡先(次の賃借人)に引き継ぐことができます。ここで注意すべきことは2つあります。まず、1つ目としては、一般的に賃貸借契約においては、退去時の原状回復義務が規定されており、居抜き物件として造作譲渡をすることが想定されていません。必ず、事前に造作譲渡をすることができるのか、賃貸人に確認をし、承諾をとってください。2つ目は、結果的に譲渡先が見つからなければ、造作譲渡は成立しません。成立しなければ、原状回復義務を引き継ぐことができません。居抜き物件としての価値を高めるためにも常にきれいに保つこと、不具合のある機器がある場合には、当該機器を入れ替える、または修繕などをするなどして、そのままの状態で放置しないようにしましょう。
◆おわりに
ここまで敷金や保証金にまつわる話をしてきましたがいかがでしたでしょうか。敷金や保証金について、意外と知らないことが多かったのではないかと思います。敷金や保証金についてのあれこれを学んだ上で、退去時に預け入れている金銭がどのくらい戻ってくるのかは想定しておくべきです。こんなはずではなかったとならないように、店舗物件の賃貸借契約を締結する前に、しっかり契約内容の確認をするようにしてください。
RESTAは店舗専門の不動産業者「レスタンダード株式会社」が提供するWEBマガジンです。飲食店の開業のノウハウから新規出店情報、飲食店経営に関わるヒント等役立つ幅広い情報を発信しています。
- 居抜き市場会員登録はこちらから
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
「開業ノウハウ」の関連記事
関連タグ
![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)