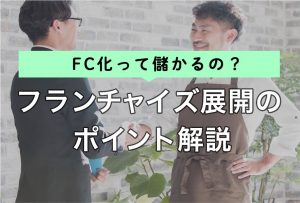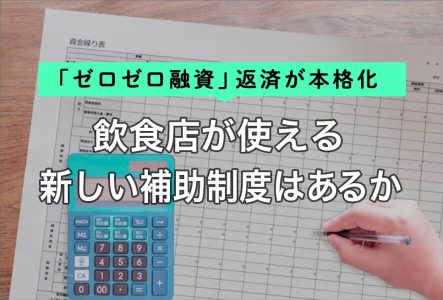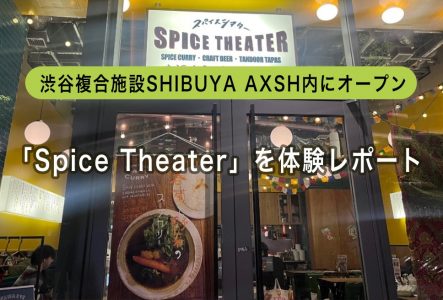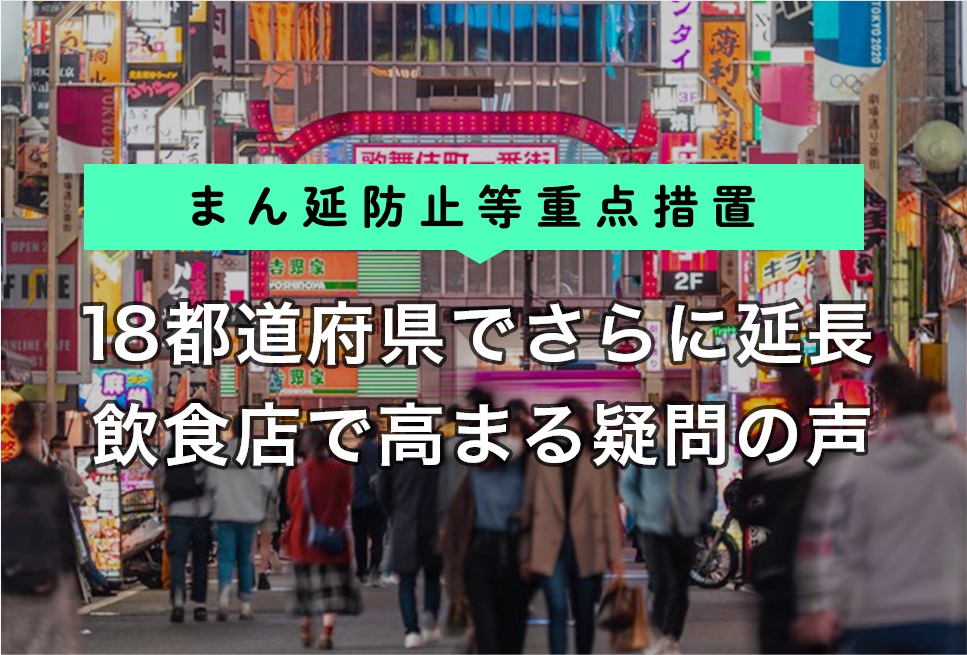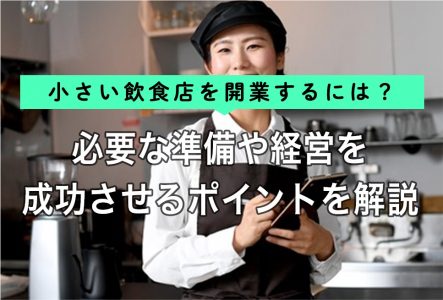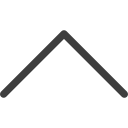ラーメン店に麺類製造業許可は必要か?基準や飲食店営業許可との関係を解説
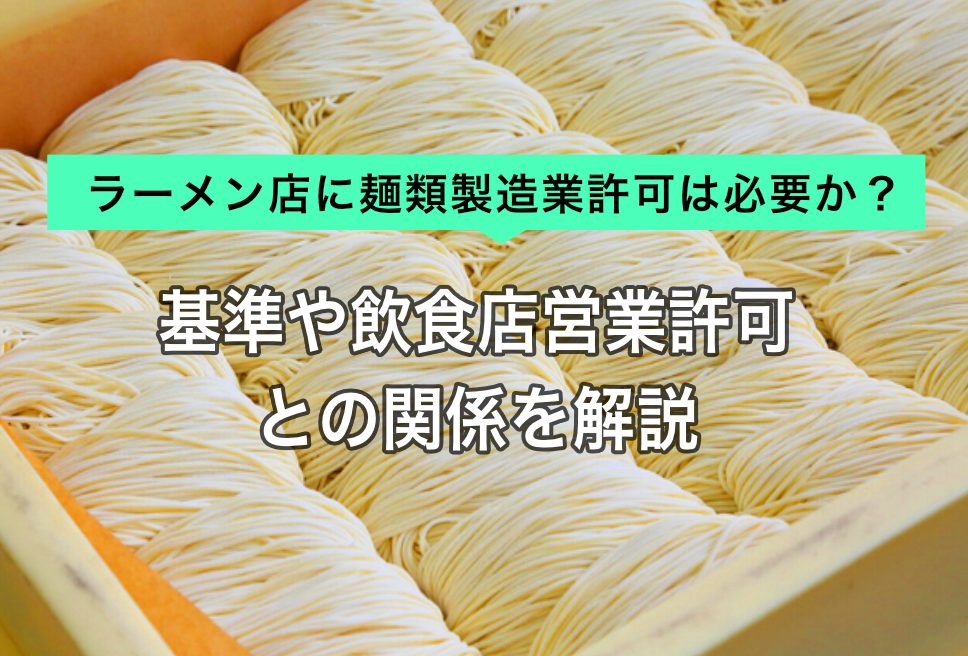
現状、食品に関する営業許可は、いくつもあり複雑な制度になっています。ラーメン店を開業する場合は、基本的に飲食店営業許可のみで問題ありません。また、同一施設内で自家製麺をする場合もこの飲食店営業許可の範囲で行うことができます。ところが、別に麺類製造業許可が必要となるパターンがいくつか存在します。これを知らずに無許可で営業すると罰則の対象となってしまいます。ここでは、麺類製造業許可について掘り下げ、基準や飲食店営業許可との関係などを中心に解説していきたいと思います。ラーメン店の出店を検討している方は、ぜひ、本記事を参考にしてください。
目次
◆ラーメン店の開業に必要な飲食店営業許可
ラーメン店を開業する際には、飲食店営業許可が必要となります。飲食店営業許可は、食品衛生法の規定に基づき食品の安全性を保障するための許可になります。対象となる営業形態としては、店舗内で調理した食品をその場で提供する、客席を設けて飲食させる場合がこれに該当します。飲食店営業許可の手続きについては、店舗を管轄する保健所に、事前相談・申請をし、審査を経て許可を得る流れとなります。この営業許可には有効期限が設定されているため、引き続き、営業許可期限満了後も営業をする場合には、所定の期間までに更新手続きを完了させなくてはなりません。
◆麺類製造業許可とは?
食品衛生法の要許可業種と届出が不要になっている業種以外の営業者は、管轄の保健所に必要な届出をしなければなりません。麺類製造業は、食品衛生法の要許可業種となるため、許可が必要となります。具体的にはこの営業は、その名称のとおり、生麺、ゆで麺、乾麺、冷凍麺などの麺類を製造する営業者が該当します。ラーメン店を開業する場合、飲食店営業許可は必須となりますが、麺類を製造する営業者の要件に該当すると、麺類製造業許可もあわせて必要となりますので、注意してください。
◆麺類製造業許可が不要な場合
麺類を製造しない場合は、麺類製造業許可は必要ないことは当然ですが、製造するとしても以下の場合には不要となります。
◇飲食店舗内で自家製麺をする
自家製麺とは、自身で製造した麺で、自身の飲食店舗で使用する麺のことを言います。手打ち麺や製麺機で製麺する方法がこれにあたります。飲食店舗内で製造することが要件で、この場合、麺類製造業許可は不要となります。飲食店営業許可のみで問題ないです。
◆麺類製造業許可が必要な場合
主に以下の場合、麺類製造業許可が必要となります。
◇他の飲食店や業者向けに製造販売(卸売り)をする
製造した麺を業務用として他の飲食店や業者向けに販売(卸売り)をする場合は、麺類製造業許可が必要となります。
◇セントラルキッチンなどで製麺して各店舗に供給する
食品工場などで大量に製麺をする、またはセントラルキッチンなどで製麺をして自身が経営するラーメン店各店舗に供給する場合は、麺類製造業許可が必要となります。
◇飲食店舗内で製麺をして小売販売をする
飲食店舗内で製麺をして持ち帰り販売やネット販売など麺をパックして小売販売する場合、麺類製造業許可が必要となります。具材やスープも同様に販売する場合は、そうざい製造業が、チャーシューも同様に販売する場合は、食肉製品製造業の許可が必要となることもあるため、事前に保健所に確認するようにしてください。
◆麺類製造業の許可申請
麺類製造業を営業の許可を受ける場合、都道府県知事が定めた基準に適合させなければなりません。この基準は、自治体ごとに異なるものとなっているので事前に確認が必要です。申請については、麺類を製造する場所の所在地を管轄する保健所に対して行い、基準等に適合しているかどうかの確認についてもこの保健所が行うことになります。まずは、事前相談をすることから始めてください。
◆食品衛生責任者の資格
麺類製造業を営業する場合、各営業所に食品衛生責任者を選任しなければなりません。食品衛生責任者とは、食品衛生法に規定された営業所で衛生管理等を行う責任者で国家資格になります。食品衛生責任者についての詳細は、「食品衛生責任者の資格を取るには?費用や試験、申し込み方法について解説します」を確認してください。さて、この食品衛生責任者ですが、ラーメン店を営業する場合、飲食店営業許可の取得が必要で、その際に合わせて取得することになります。ですので、麺類製造業を営業する場合、同一施設内での営業であれば、飲食店営業許可における食品衛生責任者がこれを兼任することができますので、新たに取得する必要はありません。
◆HACCP(ハサップ)に基づいた衛生管理を行う
HACCP(ハサップ)とは、厚生労働省のHPによると食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程のなかで、これらの危害要因を取り除き、または低減させるために特に重要となる工程について管理をし、製品の安全性を確保しようとする衛生管理における手法で国際的に認められている手法であると明記されています。Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとってHACCPとなります。麺類製造業において、許可を得るためにはこのHACCPに従った衛生管理が求められるので事前に内容をチェックしておきたいです。併せて、厚生労働省が発行している「食品製造におけるHACCP入門のための手引書[麺類編]」も確認するようにしてください。
参考: HACCP(ハサップ)-厚生労働省
◆食品表示法に基づき表示ラベルの貼付が必要な場合
食品衛生法、健康増進法、JAS法にそれぞれ分けて定めていた食品の表示についてまとめたものが食品表示法になります。この食品表示法は、販売の用に供する食品に関する表示が対象となり、様々な食品表示基準があり、商品の製造、加工、販売者はこれを遵守しなければなりません。違反した場合、罰則の対象となります。製麺をして持ち帰り販売やネット販売など麺をパックして小売販売する場合、食品表示法の対応として、消費者に分かりやすい場所にわかりやすい表現で表示ラベルを貼付しなければなりません。この表示ラベルの記載すべきものとしては、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、使用上の注意(生麺を製造・販売する場合)、製造者があります。なま、ゆでなど麺の状態については、名称に記載をしなければなりません。罰則の対象にもなるので、事前に食品表示法の規制内容を自治体等に確認をするようにしてください。
◆無許可で麺類製造業営業すると罰則はあるか
無許可で麺類製造業を営業すると、食品衛生法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せれてしまうことになります。また、さらに営業も停止しなければならなく、2年間は同許可の取得ができなくなるため、大きな痛手となります。このことは、知らなかったでは済まされなく、厳しい罰則により、経済的および社会的にダメージを負うことになるので、必ず許可を得てから営業をするようにしてください。
◆おわりに
ここまで麺類製造業許可について、幅広く解説をしてきました。食品に関する営業許可は、各都道府県知事が定める基準に適合させた上で、許可を受けなければなりません。ケースによっては複数の営業許可(移動屋台でラーメンを提供する場合は、その車両ごとに飲食店営業許可、自家製の麺類を冷凍食品として提供する場合は、食品の冷凍又は冷蔵業許可)を取得しなくてはならないこともあります。ラーメン店においてどのような形態で何を提供するのか、その際、必要となる手続きはどのようなものがあるのかについて、事前にしっかり確認をするようにしてください。
RESTAは店舗専門の不動産業者「レスタンダード株式会社」が提供するWEBマガジンです。飲食店の開業のノウハウから新規出店情報、飲食店経営に関わるヒント等役立つ幅広い情報を発信しています。
- 居抜き市場会員登録はこちらから
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
「開業ノウハウ」の関連記事
関連タグ
「まん延防止等重点措置」18都道府県でさらに延長、飲食店で高まる疑問の声
「まん延防止等重点措置」18都道府県でさらに延長、飲食店で高まる疑問の声
![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)