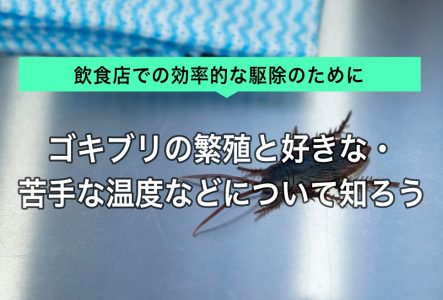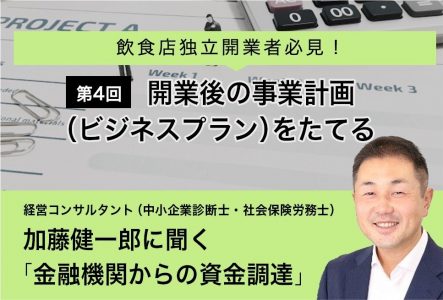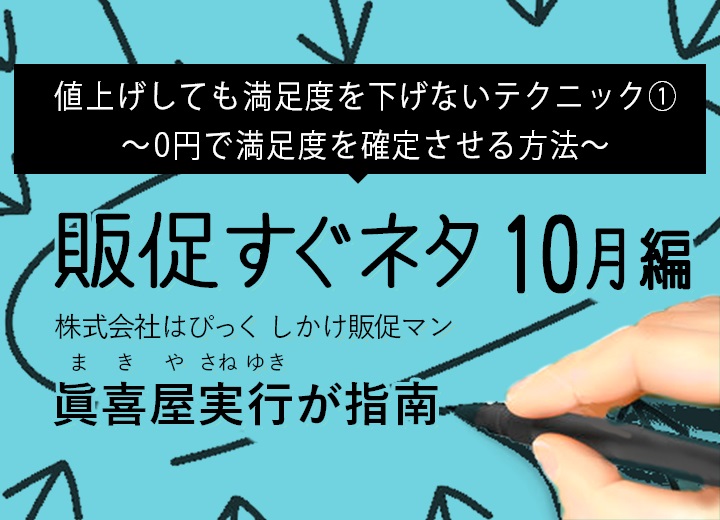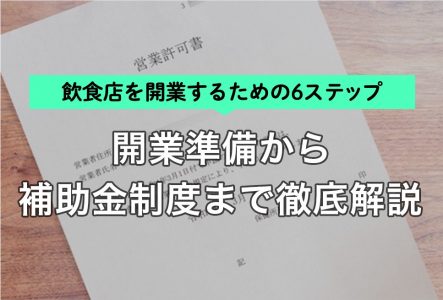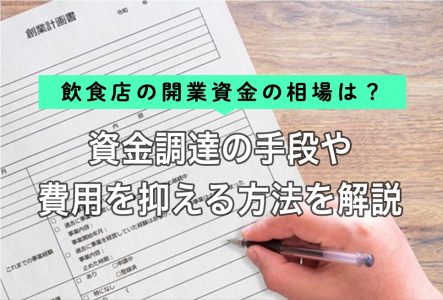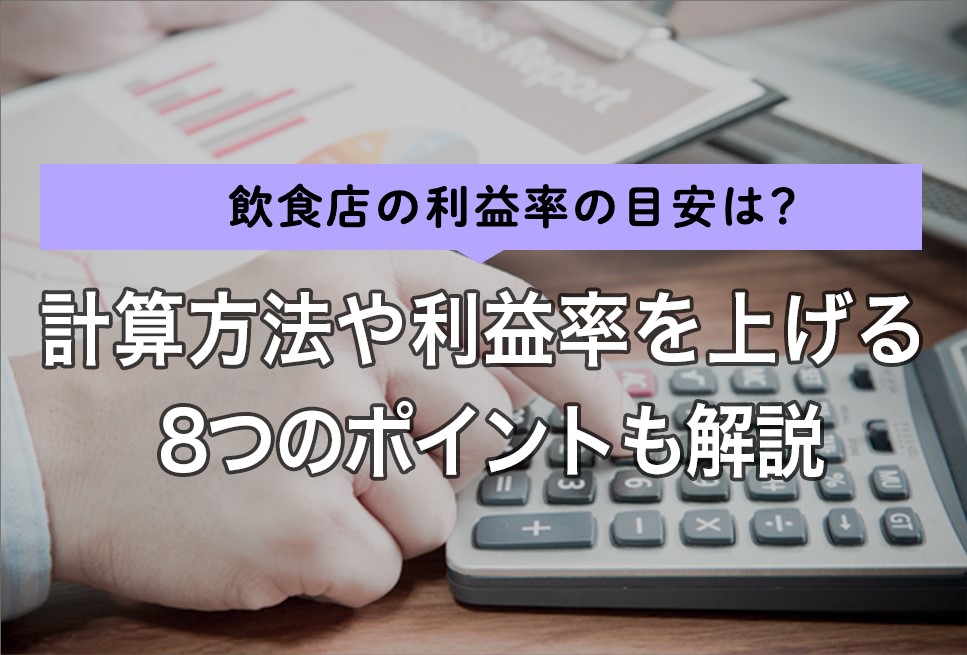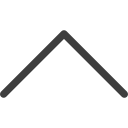食品衛生責任者は更新しなければならない?資格の概要や取得の方法について解説
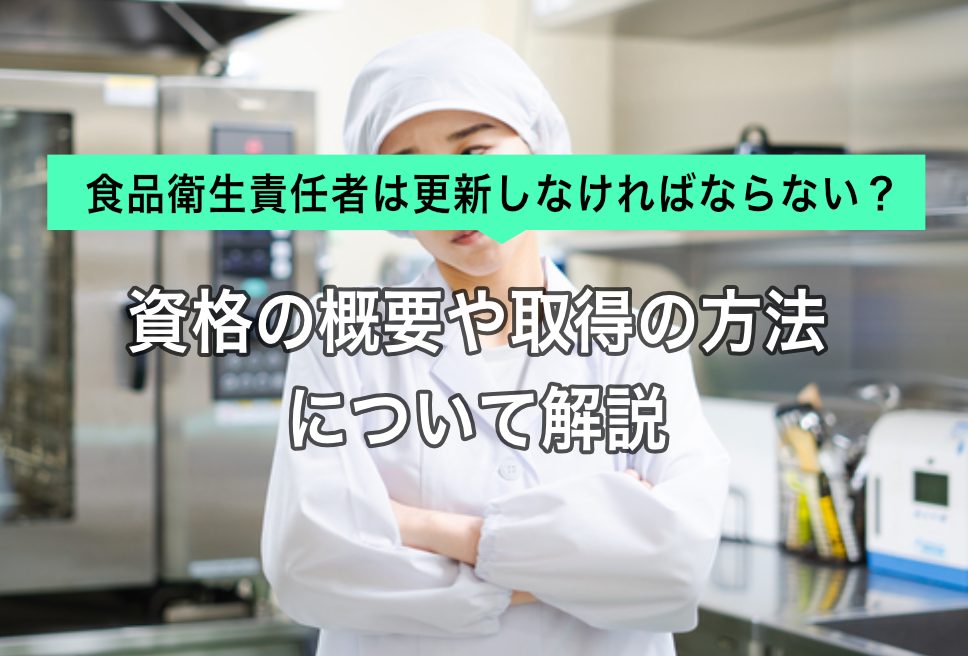
飲食店の経営をするにあたって、さまざまな資格や許可を得る必要がありますが、そのうちの1つが食品衛生責任者です。この記事では、食品衛生責任者の概要をはじめ、資格の更新の必要性や取得する方法などについて解説します。食品衛生責任者に関するよくある質問も取り上げるため、興味を持った人はぜひ最後までご覧ください。
目次
◆食品衛生責任者とは
食品衛生責任者とは、レストランをはじめとする食品を扱う施設において、食品の衛生管理の役割を担う人です。2021年6月に行われた食品衛生法の改正によって、許可や届出の対象となるすべての飲食関連施設で設置が必要になりました。具体的な仕事内容として、食品の保管や管理をする設備の衛生状態の確認、改善などが挙げられます。
なお、現在の食品衛生責任者は、食品の安全性を確保する衛生管理の手法である、HACCP(ハサップ)に沿って衛生管理を行わなければなりません。
HACCPは食品の安全を確保するための管理手法として、2021年6月から導入・運用が完全義務化されました。それぞれのアルファベットは以下の意味を持ちます。
・Hazard(危害)
・Analysis(分析)
・Critical(重要)
・Control(管理)
・Point(点)
食中毒などの健康危害を及ぼす要因を特定し、入荷・製造・出荷までの各工程でリスク管理を徹底することで、問題のある食品の出荷を防ぐことが可能です。
◇調理師免許との違い
食品衛生管理者と混同されやすいものとして、調理師免許が挙げられます。どちらも食品関連の資格ですが、調理師免許は料理の調理、および提供に必要な資格です。つまり、業務内容が大きく異なっています。なお、給食調理員をはじめとする公共性の高い職場では、調理師免許の有無が採用に大きく影響するケースもあります。
◇食品衛生管理者との違い
食品衛生管理者も、食品衛生責任者と混同されやすい資格の1つとして挙げられます。食品衛生管理者は、以下のような衛生上の考慮が必要な食品の製造、および加工をする工場で必要な資格です。厚生労働省が管轄する国家資格であり、試験の難易度も食品衛生責任者より高く設定されています。
・肉
・魚
・乳製品
◆食品衛生責任者の資格取得によって得られる知識
食品衛生責任者の資格を取得することで、どのような知識を得られるのか、以下で詳しく解説します。
◇食品衛生法に関する知識
資格の取得によって得られる知識の1つとして、食品衛生法に関する知識が挙げられます。食品衛生法とは、飲食によって発生する問題を防止するために定められた法律です。万が一食中毒や異物混入などが発生してしまうと、大規模な被害を生み出すリスクがあります。食品衛生法を知り、遵守すれば、安心かつ安全な食事を提供しつつ、消費者からの信頼を得ることが可能です。
◇食品衛生学に関する知識
食品衛生学も、食品衛生責任者の資格取得によって得られる知識です。食品衛生学とは、食品の安全性を確保するための学問分野です。具体的には、食中毒の原因となるウイルスや細菌について学んだり、食品添加物や農薬が人体にどのような影響を与えるかを学んだりします。食品衛生学に対する理解は、食中毒の予防や衛生管理の意識を高めるためにも重要です。
◇公衆衛生学に関する知識
食品衛生管理者の資格を取得すると、公衆衛生学に関する知識も習得できます。公衆衛生学とは、集団の病気を予防し、健康を促進するための学問です。具体的には、病気の予防や環境衛生などについて学びます。公衆衛生学を理解できれば、個人だけでなく社会全体の健康に貢献できます。
◆食品衛生責任者を取得する方法
食品衛生責任者の資格を取得する方法は、現状では2通りあります。以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。
◇栄養士・調理師などの資格を取得する
栄養士や調理師などの資格を取得している人は、食品衛生責任者の資格も取得できます。なお、栄養士や調理師以外にも、以下を取得している人も食品衛生責任者の資格取得が可能です。
・製菓衛生士
・船舶料理士
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・食品衛生管理者または食品衛生監視員の資格要件を満たす者
◇資格者養成講習会を受講する
オーソドックスな食品衛生責任者の資格取得方法として、資格者養成講習会の受講が挙げられます。講習会では、食品衛生学と食品衛生法、公衆衛生学の計3科目の学習、そして確認試験が実施されます。受講資格は17歳以上であることで、経歴や学歴は特に問われません。なお、高校生の受講は認められていないため、注意してください。
◆食品衛生責任者の更新は必要?
食品衛生責任者は更新が義務付けられていない資格です。そのため、一度取得してしまえば、更新せず一生使い続けられます。ただし、地域によっては数年おきに実務講習への参加が必須、または推奨されているケースもあります。気になる人は、各都道府県の保健所が管轄する食品衛生協会の公式サイトを確認しましょう。
◆地域ごとの食品衛生責任者の実務講習会
食品衛生責任者の実務講習会は、地域ごとに詳細が異なっています。以下では、東京をはじめとするエリアごとの実務講習会の内容について解説します。
◇東京の場合
東京都の市区町村では、最新の食品衛生に関する事項について学ぶために、実務講習会を実施しています。実務講習会で取り扱っている内容は市区町村ごとに異なりますが、大田区で実施されている実務講習会の内容は以下のとおりです。
・食中毒防止のための基礎知識
・食品衛生法
・食品衛生に関する情報
◇大阪の場合
大阪でも、食品衛生についての新しい知見を習得するために、実務講習会を実施しています。大阪の実務講習会の最大の特徴は、eラーニング(インターネット視聴型)を採用している点です。動画を視聴するだけで実務講習会の受講が完了するため、遠隔地にいる人や予定を空けられない人も安心です。
◇新潟の場合
営業許可施設や給食施設に勤めている食品衛生責任者について、新潟では定期的に実務講習を受けることを努力義務としています。なお、その他の施設の食品衛生責任者は努力義務の対象外です。しかし、法律をはじめとする情報の更新のためにも受講が推奨されています。受講の頻度は4年に1度で、対象者には事前に実務講習の案内が届きます。
◇広島の場合
広島市では事業主に対して、食品衛生責任者に実務講習を受けさせるように指示を出しています。これは食品衛生法において、食品衛生責任者は「食品の安全性を確保するための知識の習得に努める必要がある」と定められているためです。なお、受講する時期は営業許可、もしくは施設認定の更新手続きをした日の翌月から6か月以内です。
◇長野の場合
長野県でも、食品衛生責任者実務講習の受講が推奨されています。長野では、飲食店関係、製造加工業、そして販売業の3つの業態毎に、3年周期で実務講習が開催されています。そのため、自身が営業する業態の講習会が開催される年度のものを受講しましょう。なお、集合型講習会以外にも、遠隔地の人向けにオンラインでの実務講習も開催されています。
◆食品衛生責任者に関するよくある質問
最後に、食品衛生責任者に関するよくある質問、そしてそれぞれの質問に対する回答について解説します。
◇食品衛生責任者はどこでも有効?
1997年以降に取得した場合は、取得した都道府県以外でも有効です。これは、1997年より食品衛生責任者の養成講習会のカリキュラムが、全国で統一されたためです。なお、再受講する場合は自治体ごとに条件が異なるため、事前に確認しておきましょう。
◇食品衛生責任者がいないとどうなる?
飲食店の経営をするにあたって、原則営業許可と食品衛生責任者の設置は義務です。そのため、食品衛生責任者がいないと、営業そのものができなくなってしまいます。なお、食品衛生責任者がいない状態で営業をしてしまうと、行政処分として指示や営業停止などの対象になります。2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です
◇資格者養成講習会を受講する際に必要な持ち物と当日の流れは?
資格者養成講習会を受講する際の持ち物は、以下のとおりです。
・受講票
・筆記用具
・昼食
・受講料1万円(教材費込み)
・受講票の記載を確認できるもの
また、当日の資格者養成講習会は、次のような流れで進行します。
1.入室
2.講義開始
3.テストの実施
4.修了証書を受け取る
なお、最後に実施されるテストは3択式の問題が5問出題されます。落とすことが目的のテストではないため、あまり心配しすぎないようにしましょう。
◆まとめ
食品衛生責任者は、一度取得してしまえば更新は特に必要なく、どの都道府県でも有効です。安心・安全な食品衛生管理のために必要な資格なので、これから飲食店を始める人は取得しましょう。なお、飲食店を始められる物件を探している場合は、居抜き市場がおすすめです。店舗専門の不動産業者であり、飲食店の出退店に関する知識が豊富な点が強みとして挙げられます。
開業のノウハウをはじめ、飲食店経営に役立つ幅広い情報を発信しているため、興味を持った人はぜひ参考にしてください。
- 居抜き市場会員登録はこちらから
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
「開業ノウハウ」の関連記事
関連タグ
![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)