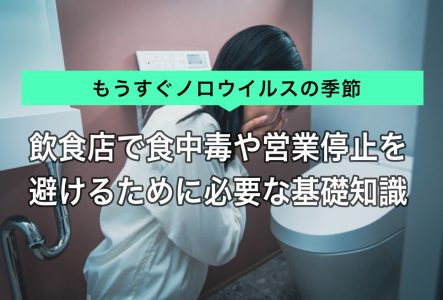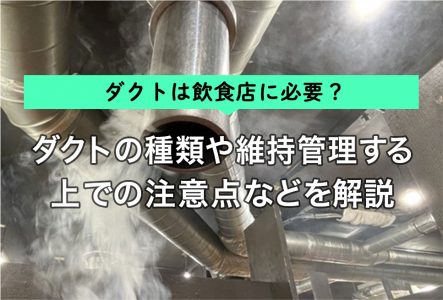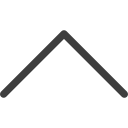飲食店営業許可の取得条件とは?申請手順やよくある質問について解説
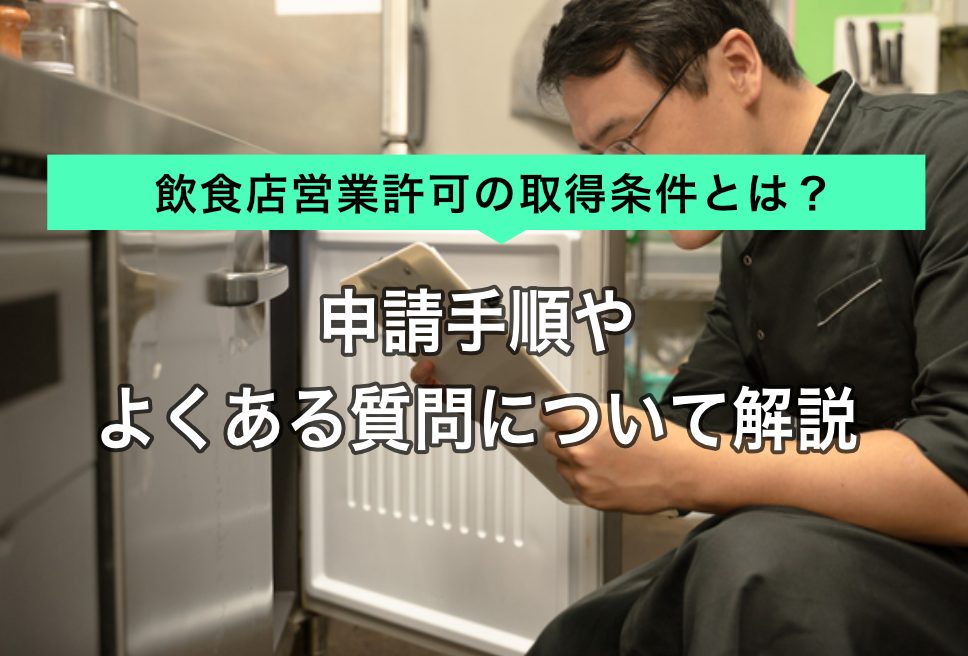
飲食店が営業を始める場合、事前に営業許可を得る必要があります。ただし、許可を得るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。この記事では、飲食店が営業許可を得るための条件をはじめ、取得までの流れやよくある質問などを解説します。飲食店の経営者や、これから飲食店を始めたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
◆飲食店の営業許可とは
飲食店の営業許可は、飲食店を開業するにあたって必要な公的な許可です。食堂をはじめ、許可が必要な飲食店の業態はさまざまなため、自分の店舗は開業許可が必要か否か事前に調べておきましょう。なお、営業許可を得ずに開業してしまうと、無許可営業となり罰則の対象となります。具体的には2年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科されるため、注意しましょう。
※参考:食品衛生法 | e-Gov 法令検索
◆一般的な飲食店の営業許可に必要な条件
一般的な飲食店が営業の許可を取得するにあたって、満たさなければならない条件について解説します。
◇飲食店営業許可証
飲食店営業許可証は、管轄の保健所に申請書類を提出し、検査に合格することで取得できます。別の場所に複数店舗営業する場合は、店舗ごとに飲食店営業許可証を取得しなければなりません。また、飲食店営業許可は場所や設備に対して出される許可のため、届出を出せば経営者が交代しても許可を引き継ぐことが可能です。
◇食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者は、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理を行う人です。食品衛生責任者は調理師や製菓衛生士など、特定の資格を有する人だけがなれます。食品衛生責任者は1店舗に1人置く必要があり、1人が複数店舗を掛け持ちするのは認められていません。資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を修了することで取得できます。
◆状況によって飲食店の開業に必要な営業許可証の種類
状況によっては、追加で用意しなければならない営業許可証もあります。どのような営業許可証が必要になるかは、以下で解説します。
◇深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜0時から午前6時までの深夜帯に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な店舗の種類として、居酒屋や立ち飲み屋、ダイニングバーなどが挙げられます。なお、ファミレスをはじめとする、食事をメインに提供する店舗の場合は、届出を出さなくても酒類の提供が可能です。
※参考:Taro-風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
◇防火管理者の設置
防火管理者とは、収容人数が30名以上の規模の飲食店を開業する場合に必要な資格です。防火管理者の所有者は、消防計画をはじめ、各種防火対策を行う役割を担います。この資格を取得するためには、防火管理講習を受講しなければなりません。防火管理者には甲と乙の2種類があるため、自分の店舗がどちらの資格を必要としているのか事前に調べておきましょう。
※参考:防火管理者が必要な防火対象物と資格 | 東京消防庁
◇そのほかに必要な営業許可証
飲食店は、提供する飲食の種類、業務形態などによって必要な資格が異なります。たとえば、クッキーをはじめとする菓子類を提供するためには菓子製造業許可が、乳製品を提供するためには乳製品製造業許可が必要です。どの資格が必要なのかわからない場合は、事業計画書を持って管轄の保健所に相談しましょう。
◆飲食店の営業許可を得るまでの流れ
飲食店が営業許可を得るにあたって、どのような流れを辿るかについて解説します。
◇1. 保健所に相談する
最初にやることは、管轄の保健所への相談です。飲食店の営業許可を得るにあたって、細かい要件やローカルルールが存在します。工事後に指摘を受けた場合、手直しのために追加で費用を用意しなければならず、経済的な負担が大きくなります。事前にチェックやアドバイスを受ければ、スムーズに審査や点検を進めることが可能です。
◇2. 飲食店営業許可の申請を行う
保健所での相談をとおして必要な情報が集まったら、申請の準備を進めましょう。以下は、申請をするにあたって必要な書類の一覧です。
・営業許可申請書
・施設構造と設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水質検査成績書
・登記事項証明書(法人の場合)
申請をスムーズに進めるためにも、事前に提出書類に抜けや漏れがないか確認しましょう。
◇3. 保健所による立入検査を受ける
営業許可の申請後、担当者が実際に店舗に足を運び、問題がないか内部をくまなくチェックします。立入検査のチェックポイントの一例は、以下のとおりです。
・2槽以上のシンクや給湯設備があること
・厨房と客席の区画が必須
・従業員用とお客様用に分かれた手洗い場があること
・蓋付きゴミ箱の設置の有無
・照明の明るさ(100ルクス程度以上)
検査基準や項目は保健所によって異なるため、事前に確かめておきましょう。
◇4. 飲食店営業許可証を受け取る
施設検査に合格すると、飲食店営業許可証が交付されます。交付方法は窓口での受け取り、郵送などさまざまです。そのため、事前相談や立入検査の際に、あらかじめ交付方法を聞いておくのをおすすめします。なお、受け取った飲食店営業許可証はお客様が安心して利用できるように、店舗の見える場所に掲示しましょう。
◇5. 消防署に防火管理者を届け出る
飲食店の営業開始前までに、消防署に防火管理者を届けましょう。届出書は、消防署の公式サイトからダウンロードできます。なお、届出は新しい設備を導入した場合や、店舗の改装を行った際なども必要です。届出を忘れてしまうと、罰金や営業停止などの厳しい制裁が科されるため、忘れないように注意しましょう。
◇6. 飲食店の営業を開始する
営業許可を取得し、防火管理者の届出が完了すれば、飲食店の営業を始められます。営業許可証には有効期限(一般的に5〜8年)があり、長期間営業する場合は更新が必要です。更新時には飲食店営業許可証と所定の更新料を用意しましょう。
◆飲食店の営業許可に関するよくある質問
最後に、飲食店の営業許可に関するよくある質問と回答について解説します。
◇自宅での飲食店営業も許可は必要?
自宅で飲食店を営業するときも許可を取得しなければなりません。自宅で飲食店を営業する場合、小規模から始められる、通勤時間がかからないなどのメリットがあります。しかし、許可を得るハードルが通常の飲食店よりも高いため、事前に入念な準備をする必要があります。
◇飲食店で営業許可が不要な場合はある?
営利目的で飲食店を営業する場合、原則として営業許可を取得しなければなりません。店舗を持たない屋台、キッチンカーなども同様です。しかし、子ども食堂に代表される福祉目的の施設については、営業許可はとくに必要ありません。ただし、都道府県によっては営業許可の取得を推奨しているケースもあります。
◇保健所の検査に落ちたらどうなる?
営業許可申請後に実施される立入検査は、検査項目をすべてクリアする必要があります。1つでも基準に満たない項目があると、検査に落ちてしまい、営業許可がもらえません。万が一落ちてしまった場合は、まず基準をクリアできなかった理由を明確にしましょう。問題点を改善した上で、再度審査の申請が必要です。
◇飲食店営業許可の取得にかかる費用と期間の目安は?
飲食店営業許可の取得にかかる費用は、管轄の保健所によって異なります。たとえば、東京都なら1万8,000円、神奈川県なら1万6,000円かかります。また、飲食店営業許可の申請から取得までは、3週間程度かかるのが一般的です。正確な費用や期間を知りたい場合は、保健所に相談する際に確認しておきましょう。
※参考:東京都食品衛生関係許可手数料 ※令和6年6月1日から適用
※参考:営業許可申請手数料について – 神奈川県ホームページ
◆まとめ
飲食店を営業するには、飲食店営業許可証の取得をはじめ、さまざまな条件を満たさなければなりません。営業形態によって営業に必要な条件も異なっているため、事前にしっかり情報収集を行いましょう。もし飲食店の営業に関する情報を知りたい場合は、居抜き市場をチェックしてください。
居抜き市場は、居抜き物件を中心に扱っている不動産業者です。飲食店の出退店に関して熟知しており、開業のノウハウをはじめ、飲食店経営に役立つ幅広い情報を発信しています。興味を持った人は、ぜひ参考にしてください。
- 居抜き市場会員登録はこちらから
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
「開業ノウハウ」の関連記事
関連タグ
![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)