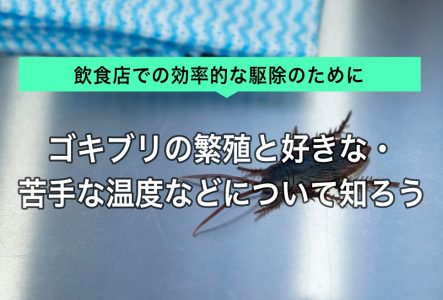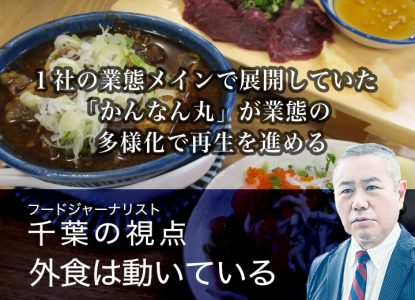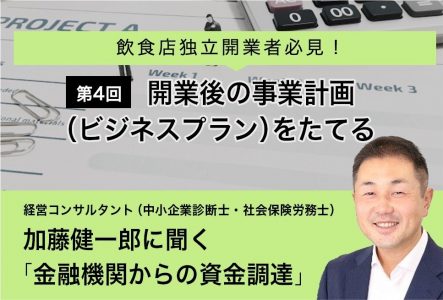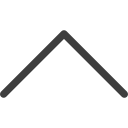店舗の賃料や仲介手数料に消費税はかかる?テナントで課税対象となる費用を解説
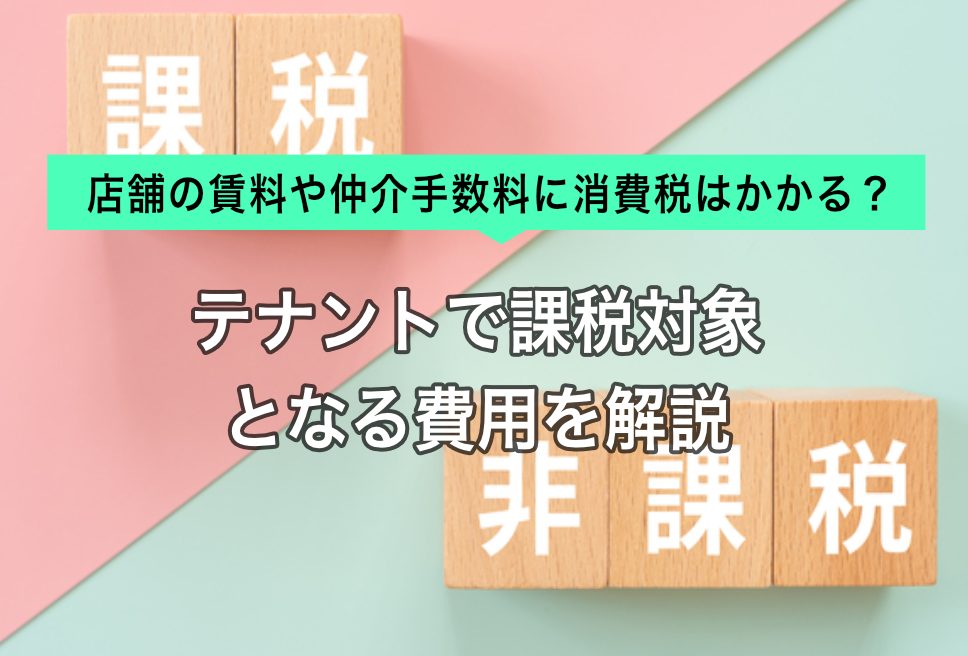
店舗物件を借りる際に、毎月発生する支払いとして賃料がありますが、この賃料には消費税がかかることをご存じでしょうか。住宅物件の場合、家賃に消費税がかからないので、店舗も同じではと思う方も多いかと思います。本記事では、賃料だけでなく仲介手数料や造作譲渡代金などテナントにかかる課税対象となる費用について幅広く取り上げていきます。
目次
◆店舗の賃料には消費税がかかる。
店舗を開業するにあたって収支計算をしたり事業計画書を作成したりする際に見落としがちなこととして、店舗物件の賃料は「消費税がかかる」ということが挙げられます。後々、事業計画を見直さなくてはならない事態にならないようにするために消費税に関する知識は必須です。さて、日本において消費税というものが導入された当時、住宅の家賃はその対象とされていました。しかし、1991年以降、社会政策上の特例として住宅物件は非課税の対象に分類されることとなりました。このような背景があること、また、現に住宅物件の家賃に消費税がかかっていないことが、店舗の賃料に消費税がかかることを知らない人が多いことの理由ではないかと推察されます。店舗(事業用)の物件は消費税がかかり、住宅物件はかからないと覚えておいてください。
◆テナントにかかる費用で課税の対象となるものは?
テナントにかかる費用で課税の対象となるものは、賃料のほか様々なものがあります。以下、それぞれの項目別に確認をしていきます。
◇仲介手数料
仲介手数料は、物件の契約を仲介する不動産業者に対して支払う費用です。その金額は、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣によって規定されており、賃貸物件の場合、賃料の1か月分に消費税を加えたものが上限額とされています。この仲介手数料ですが、消費税の対象です。仲介手数料というのは事業者である不動産業者が行った仲介業務についての報酬であって賃貸人に対して支払うものではありません。賃料とは異なります。消費税は、事業者が事業として行う取引に対して広く公平に発生する税のため、消費税が発生することになります。
◇礼金
礼金は、物件を契約する際に賃貸人に対して支払う費用です。礼金の成り立ちには諸説ありますが、関東大震災で住宅の倒壊や火災などにより住むところをなくした人々が、住宅を借りる際になかなか空いている物件がないなかで、なんとか借りることができた際に、賃貸人に対して、そのお礼として支払った金銭であると言われています。その他の説として、高度経済成長期のなか、上京する学生の親御さんが、下宿先の賃貸人に対して、「うちの子をよろしくお願いします。」という意味を込めて支払った金銭が礼金である、というものもあります。いずれにせよ何らかの理由により支払った金銭が今もなお礼金というかたちで商慣習として残っているということです。この礼金ですが、店舗の場合は、消費税の対象です。
◇管理費・共益費
物件を借りる際、毎月の賃料とは別に管理費または共益費を支払わなければならない場合があります。物件によってはその名称が管理費であったり共益費であったりします。明確な違いを設けているわけではないので管理費と共益費はほぼ同じ意味で使用されていると考えて問題ないと思われます。この管理費・共益費ですが、店舗の場合は、消費税の対象です。
◇敷金・保証金
敷金や保証金は、債務を担保するために契約時に賃貸人に対し預け入れる金銭になります。事業として対価を得て行う取引ではないので不課税(課税対象ではない)となります。敷金・保証金の詳細については、「敷金と保証金の違いは?店舗の賃貸借契約で預託する金銭にまつわる話」を参考にしてみてください。
◇償却・敷引き(しきびき)
敷金や保証金は不課税なので、それに関連する償却や敷引きは、消費税がかからないのではと考えてしまいそうですが、賃借人に返還をしない金銭については賃貸人にとっては対価性があるので、この償却・敷引きですが、店舗の場合は、消費税の対象です。
◇更新料・更新事務手数料
更新料は、契約の更新時、賃貸人に対して支払う金銭で、更新事務手数料は、契約を更新する際に更新契約業務を行う不動産業者に対して支払う金銭となります。それぞれ支払い先が異なりますが、どちらも賃借人が負担する費用に変わりはありません。更新料も、店舗の場合は、消費税の対象です。更新事務手数料については、不動産業者に支払う費用となるので、仲介手数料と同じように消費税の対象となります。
◇造作譲渡代金
居抜き店舗として、物件を契約する場合、造作譲渡代金が発生することがあります。造作譲渡代金とは、内装、什器、備品などを前テナントから買い取る費用になります。造作譲渡代金は、事業者が事業として対価を得て行う取引に該当するので消費税の対象となります。
◆店舗兼住宅の物件の場合はどうなるのか。
店舗を開業しようとする際、店舗兼住宅(住宅付き店舗)の物件を検討している方もいるかと思います。店舗兼住宅の物件とは、住居を兼ね備えた店舗物件のことを言います。例えば、1階が店舗で2階が住宅となっている物件です。この2階の住居部分を店舗の客席として使用する、店舗の倉庫として使用する、または事務所として使用するなどといった場合は、事業用となるので消費税が発生します。店舗で1階を使用して、住居で2階を使用する(住み込み)という目的で店舗兼住宅の物件を契約される方の賃料に対しての消費税はどうなるのでしょうか。課税されるのでしょうか。国税庁によると、店舗部分と住宅部分を面積で区分して店舗にかかる賃料は課税の対象、住宅にかかる賃料は課税の対象とされません。例えば、賃料が40万だとして、1階店舗部分と2階住居部分の面積がほぼ同じであれば、賃料はそれぞれ20万となり、1階店舗部分の20万に対してのみ消費税の対象となります。その他、契約時に支払う礼金についても同様の考え方となります。物件の契約前に賃貸人、不動産業者と住居部分をどのように使用するのかの打合せをすることが重要となります。
◆事業者間の取引は、総額表示義務の対象外(外税表記が可能)
課税の対象となるかならないかの話とは別に、消費税の内税表記、外税表記についても理解しておきたいところです。2021年4月以降、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的として総額表示(内税表記)が義務付けされました。総額表示の義務は、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が表示をする価格が対象となっています。メニュー表やPOPなどで価格を明記する際に、消費税額を含んだ総額を表示(税込価格で表示)しなければなりません。一方で、事業者間(会社と会社など)の取引は、総額表示としなくても(外税表記)問題ないとされています。ここで注意しなければならないこととしては、店舗不動産を扱っている業者のWEBサイトや募集図面(チラシ)の表記方法(内税、外税)は業者によるということです。店舗物件は賃料も物件取得費も高額となる傾向があるので、当然、消費税の金額も合計すると数万円から数十万円となってしまいます。わかりやすさの点から内税表記の業者の方が良心的ではありますが、実態はどうかというと、外税表記が多いという印象です。良いと思った賃料であっても外税表記の可能性があるので、勘違いをしてしまわないためにも事前に確認をするようにしてください。
参考:
・事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方|財務省
・消費税における「総額表示方式」の概要|財務省
◆インボイス制度(適格請求書等保存方式)はテナントに関係あるか。
適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、2023年10月1日より開始され、消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。適格請求書を発行するためには税務署にて適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。売上高が1,000万円以下である免税事業者については登録しないと適格請求書を発行することができない制度となっています。賃貸人、物件の契約の仲介や建物を管理する不動産業者が適格請求書発行事業者であるかを物件の契約前までに必ず確認をするようにしてください。消費税を仕入税額控除することで納税額を減らすことができるため適格請求書の発行を取引の相手方にお願いしてください。
参考:インボイス制度について|国税庁
◆おわりに
本記事では、「店舗の賃料や仲介手数料に消費税はかかる?テナントで課税対象となる費用を解説」というタイトルでテナントにかかる費用の消費税について幅広く解説をしてきました。契約時に宅地建物取引業者から物件の重要事項説明を受ける際に消費税の存在について、「初めて知った」「うっかり見落としてしまい気が付かなかった」といったことのないように、お金にかかわる大事なこと、且つその金額も高額となるので、しっかり事業計画の段階から把握するようにしてください。
RESTAは店舗専門の不動産業者「レスタンダード株式会社」が提供するWEBマガジンです。飲食店の開業のノウハウから新規出店情報、飲食店経営に関わるヒント等役立つ幅広い情報を発信しています。
- 居抜き市場会員登録はこちらから
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
「開業ノウハウ」の関連記事
関連タグ
「CUZEN MATCHA(空禅抹茶)」を使って、1杯ごとに挽きたて抹茶!BA...
「CUZEN MATCHA(空禅抹茶)」を使って、1杯ごとに挽きたて抹茶!BA...
![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)