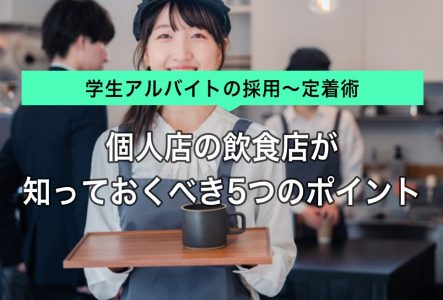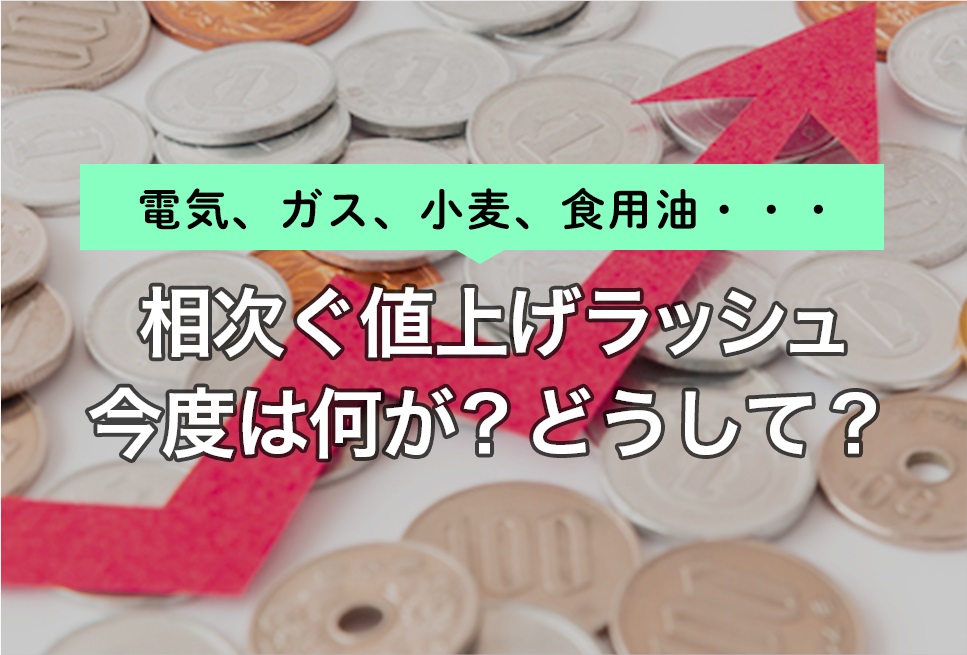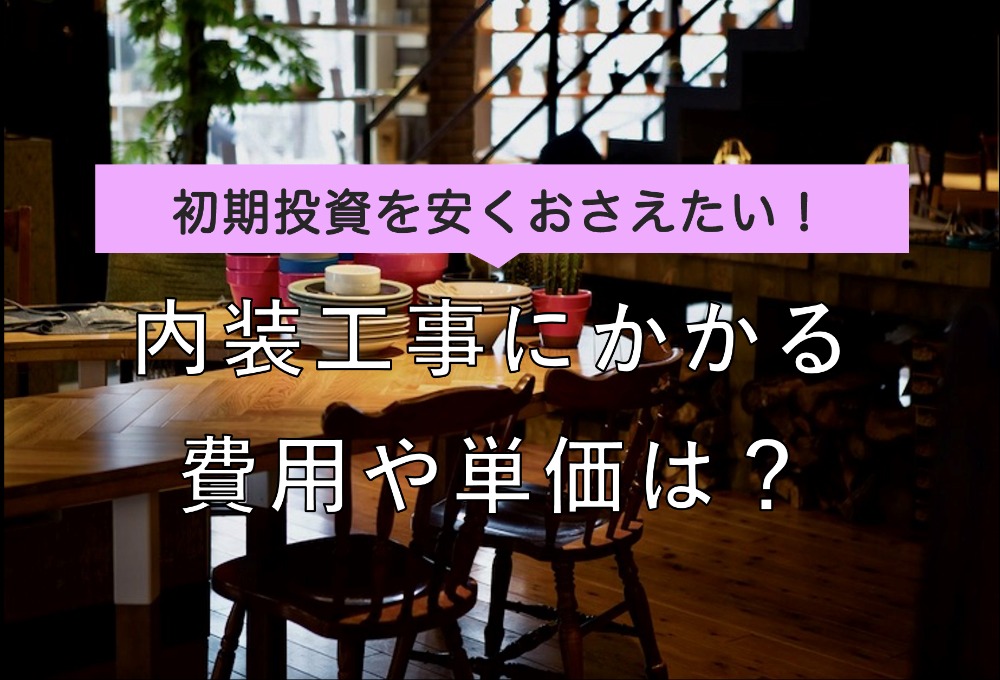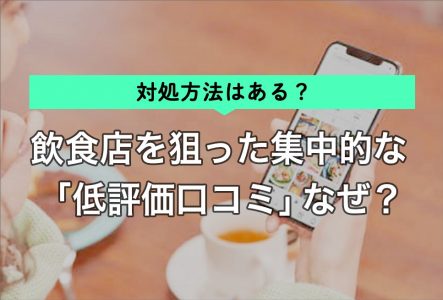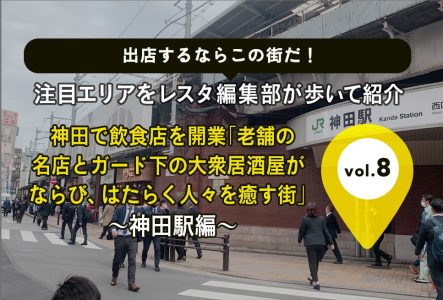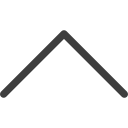飲食店営業許可証を取得するには?資格や手続き・流れ・必要書類などの方法を解説
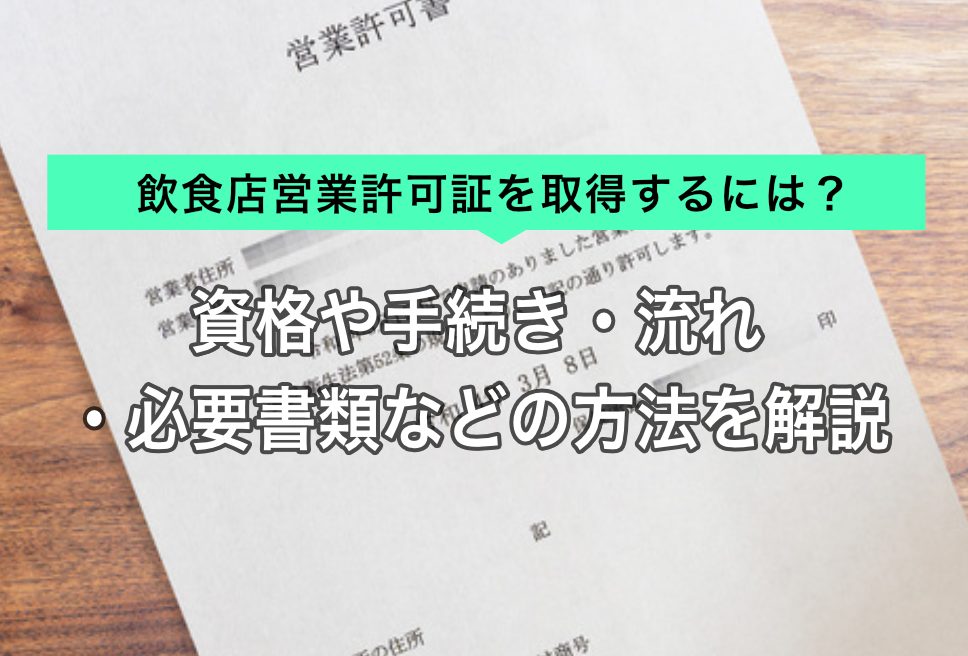
飲食店の開業に興味があっても、どのような手続きが必要であるかを知らない人もいるでしょう。この記事では、飲食店の営業許可を取得するための条件や方法、手順などを解説します。飲食店の経営に興味があり、開業に向けて知識を得たいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
◆飲食店の営業許可とは
飲食店を開業する際には、飲食店の「営業許可」を取得する必要があります。「飲食店」とは食品を調理し、販売する店舗を指します。カフェやレストラン、居酒屋、立ち呑み店などのほか、キッチンカーや屋台、イベントで出店される売店など、食品を調理して提供したい場合は、店舗の有無を問わず営業許可が必要です。
営業許可を取得するには、管轄の保健所に申請し、検査を受けて合格しなければなりません。無許可で営業をすると食品衛生法や風営法違反となります。食品衛生法違反では2年以下の懲役または200万円以下の罰金、風営法違反では無許可営業等に対する罰則の強化が図られ令和7年6月28日以降は5年以下の拘禁刑または1千万円以下の罰金が課せられます。
※参考:食品衛生法 | e-Gov 法令検索
※参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(令和7年6月28日施行)/神奈川県警察
◆飲食店営業許可を取得するための条件・方法
飲食店営業許可を取得するために欠かせない、飲食店営業許可証の取得と食品衛生責任者の設置について解説します。
◇飲食店営業許可証の取得
飲食店営業許可証は、飲食店の開業において欠かせません。営業許可証を取得するには、管轄の保健所に申請書類を提出し、実施される検査に合格しなければなりません。検査の内容は衛生面が中心で、内装や設備が飲食店に適しているかを判断します。
以前は「喫茶店営業許可証」もありましたが、2021年6月1日に食品衛生法が改正され「飲食店営業許可証」に統合されました。
◇食品衛生責任者の設置
食品衛生法により、飲食店の営業許可を取得するには、1店舗につき1名以上の食品衛生責任者の設置が義務付けられています。食品衛生責任者が日頃から店舗の衛生管理をして、飲食店内での食中毒を防ぎます。
食品衛生責任者の資格は、1日間の講習を受けることで取得できます。ただし、栄養士や調理師、製菓衛生士、船舶料理師などの資格を持っている場合には、講習が免除されます。また、と畜場法に規定する衛生管理責任者、作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者も、講習免除の対象です。
◆営業許可は飲食店の種類によって異なる
営業許可には複数の種類があります。業務形態や提供する料理の内容によって必要な申請が異なるため、開業する店舗がどの業態に該当するのかを確認しなければなりません。
たとえば、クッキーやケーキを取り扱う場合は菓子製造許可、ハムやソーセージは食肉製品製造業許可、乳製品は乳製品製造業許可、アイスクリームはアイスクリーム類製造業許可が必要です。また、ジビエ料理の提供には飲食店営業許可があれば問題ありませんが、加工には他の許可が必要です。
◇深夜酒類提供飲食店営業開始届
酒類を主力商品として、午前0時~6時の深夜帯に提供する飲食店は、飲食店営業許可だけではなく、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の申請が必要です。
ファミリーレストランのように「主食」とされる食事を中心に提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請をしなくても、夜間に酒類を提供できます。ただし、居酒屋で提供されるお茶漬けやおにぎりは「主食」には該当しません。
◆飲食店開業の必要な資格
飲食店の開業には「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格取得、または取得者を置く必要があります。
◇食品衛生責任者
飲食店には、施設ごとに食品衛生責任者を置くことが、食品衛生法によって義務付けられています。食品衛生責任者は、営業する店舗で食中毒の発生や食品衛生法違反がないかを適切に管理し、店舗の従業員に対して衛生教育を実施しなければなりません。
食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会が実施する、保健所長認定の講習会を受講することで取得できます。栄養士・調理師・製菓衛生師・船舶料理士・医師・歯科医師・獣医師・薬剤師などの食品衛生責任者資格の保有者であれば、講習を受けずに食品衛生責任者の資格取得が可能です。
◇防火管理者
不特定多数の人が出入りする防火対象物となる建物や施設においては、消防法に基づいた防火に関する講習会の課程を修了した、防火管理者が必要です。飲食店の場合には、収容人数が30人以上の規模であれば、防火管理者の設置が義務付けられています。「30人以上」とは、店舗の席数ではなく、従業員も含めた収容人数を指します。
防火管理者には、「乙種防火管理者」と「甲種防火管理者」の2種類があります。それぞれ店舗の延べ床面積の広さで区別されており、講習会の時間や受講料が異なります。
◆営業許可取得までの手続き・流れ
営業許可を取得するには、さまざまな手続きがあります。ここでは、取得までに必要な6つの手順について解説します。
◇保健所へ事前に相談する
物件と内装の計画ができたら、保健所へ事前に相談します。その際には、内装業者との打ち合わせで決まった図面を持参しましょう。不備があった場合、工事が始まる前に修正できるため、開業準備を効率よく進められます。また、保健所への営業許可の申請時には、食品衛生責任者の資格が必須です。申請前に資格を取得しておきましょう。
◇飲食店営業許可の申請書など必要書類を提出する
保健所への事前相談で問題がないと判断されたら、工事のスタートとともに営業許可の申請をしましょう。営業許可の申請に必要な書類は、営業許可申請書、店舗の見取り図・配置の詳細な図面、食品衛生責任者資格の証明書類です。
また、営業許可を取得するには、保健所による現地調査を受ける必要があります。工事の終了予定に合わせて、調査日程の手配をしましょう。
◇保健所による施設の確認検査を受ける
営業許可の申請において書類の不備がなければ、保健所による施設の確認検査が実施されます。照明の明るさや厨房内の設備、トイレの衛生面、冷蔵庫、厨房と客席の分離などが、特に重視されるポイントです。また、実際に現地を確認することで、図面どおりに工事が進んでいるか、設備基準に合致しているかを確認します。
確認したポイントが、保健所への事前相談の内容と相違なければ、大幅な改善指示は起きにくいでしょう。ただし、問題が見つかった場合は速やかに解決しなければいけません。
◇飲食店営業許可証の交付
保健所の立入施設検査の結果、問題がなければ営業許可がおります。営業許可証は保健所の窓口で受け取り、店舗内の見やすい場所に掲示します。
◇防火管理者の届出
飲食店の営業開始日までに、管轄の消防署に防火管理者の届出書を提出しなければなりません。届出書の様式は消防署のホームページからダウンロードできます。同じ内容の届出書を2通、「消防署保管用」と「事業所保管用」として用意します。届出書と併せて、防火管理者の防火・防災管理講習修了証(手帳)の原本も提出します。
◇飲食店の営業開始
営業許可証を受け取り、防火管理者の届出が終了すると、営業を開始できます。営業を開始する際には、食品衛生責任者資格証を店舗内に掲示します。開業後はホール・キッチンともに衛生管理を徹底しましょう。
◆飲食店営業許可に必要な費用と期間
飲食店営業許可は、営業開始の予定日までに必ず取得しなければなりません。ここでは、取得にかかる費用や期間について解説します。
◇飲食店営業許可の申請に必要な費用
申請には、申請手続きの手数料を支払わなければなりません。金額は地域によって異なりますが、新規取得の場合は1万6,000円〜1万9,000円、継続・更新の場合は8,000~1万2,000円です。申請料は、書類提出時に窓口で支払います。
なお、これらの手続きを行政書士事務所に依頼する場合は、3万円~10万円の手数料がかかります。
◇飲食店営業許可証取得までの期間
飲食店営業許可証を取得するまでには、約3週間かかります。日数の目安は、保健所への事前相談から申請書類作成まで約3日、保健所での申請処理に約10日、保健所の立入施設検査から営業許可がおりるまでに約1週間です。書類に不備があり再提出となると、さらに時間がかかります。
◆飲食店営業許可証の有効期限と更新
飲食店営業許可証の有効期限は都道府県ごとに異なりますが、一般的に5~8年です。期限以降も営業を続ける場合は、その都度、再検査と更新が必要です。更新手続きは、有効期限の1か月前までに申請しましょう。更新は、飲食店営業許可証と更新料を保健所の窓口に持参して、手続きをします。施設の検査を受けて合格すると、新しい営業許可証が交付されます。
申請に時間がかかる場合もあるため、余裕をもって手続きをしましょう。万が一、更新を忘れて、有効期限が過ぎたまま営業を続けると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課される可能性があるため、注意が必要です。
◆まとめ
飲食店の営業には、飲食店営業許可が不可欠です。飲食店営業許可証の申請と食品衛生責任者の設置により、営業許可を取得しなければ、営業を開始できません。営業許可証の申請には一般的に約3週間かかりますが、さらに期間を要する場合もあります。営業開始日に間に合うように、早めに準備を進めましょう。
レスタンダード株式会社は「居抜き物件掲載トップクラス居抜き市場(いちば)」を運営している、店舗専門の不動産業者です。飲食店の出退店に精通し、開業ノウハウや飲食店経営に役立つ情報を発信しています。
- 居抜き市場会員登録はこちらから
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
「開業ノウハウ」の関連記事
関連タグ
![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)